多くの中小製造業が「試作コストを減らしたい」と考え、CAE(Computer Aided Engineering)を導入しています。ところが実際には、「導入したのに効果が出ない」「試作が減らない」と感じる経営者も少なくありません。
本記事では、なぜCAEを入れても成果が出にくいのか、そして効果を最大化するために必要な運用改善のポイントを解説します。
なぜCAEを入れても効果が出ないのか?
使いこなせていない
CAEソフトを導入しても、担当者が結果を正しく読み解けていないケースが多く見られます。
解析結果が設計判断に結びつかず、結局「現物で確認する」流れに戻ってしまうのです。
つまり、ツールを持っていても「設計に活かす仕組み」が整っていなければ、投資効果は限定的です。
前提条件がずれている(設計条件の問題)
CAEは前提条件が正しくなければ、どれだけ解析精度が高くても結果は意味を持ちません。
例えば、実際の熱流体条件・取り付け剛性・放熱経路などが設計値と異なると、解析結果と実物挙動に乖離が生じます。
このように、解析モデルが理想化されすぎて現場条件とかけ離れていると、CAEの信頼性が下がり、結局試作依存が続いてしまいます。
設計者と解析者の連携不足
設計者は「早く結果が欲しい」、解析者は「条件が不明で解析できない」。
このように両者の間で情報共有が不十分なまま解析が進むと、結果が設計意図と合わず、最終的にレビュー資料として終わってしまうことがあります。
本来CAEは設計を支援するツールであり、設計と解析の連携タイミングをどう作るかが鍵です。
効果を出すための運用改善ポイント
CAE導入の成果を高めるには、単にツールを入れるだけでなく、人と仕組みの両面から改善する必要があります。
- 設計者が解析の基礎を理解する: 条件設定の重要性を知ることで、実務に合った解析が可能になる。
- 解析者が設計意図を学ぶ: 設計側の要求を理解し、「現場で使える結果」を提供できるようになる。
つまり、教育を通じて設計と解析の視点をつなぐことが、CAEを「使える仕組み」に変える第一歩です。
経営者は、ツール導入=ゴールではなく、運用設計こそが投資回収の本質であることを理解する必要があります。
まとめ:CAEの価値は「導入」ではなく「運用力」
CAEを導入しても試作が減らない最大の理由は、技術ではなく「運用の仕組み」にあります。
設計・解析・経営の3者が目的を共有し、結果を設計に反映できる体制を築くことこそが、試作削減と利益改善の最短ルートです。
CAEの価値は導入ではなく、運用力で決まる。
その意識改革が、企業全体の競争力向上につながります。
「自社のCAEの運用の仕組みついて、具体的に知りたい」と感じた方は、ぜひ無料相談(10分)をご利用ください。具体的な課題に合わせて改善の方向性をアドバイスいたします。
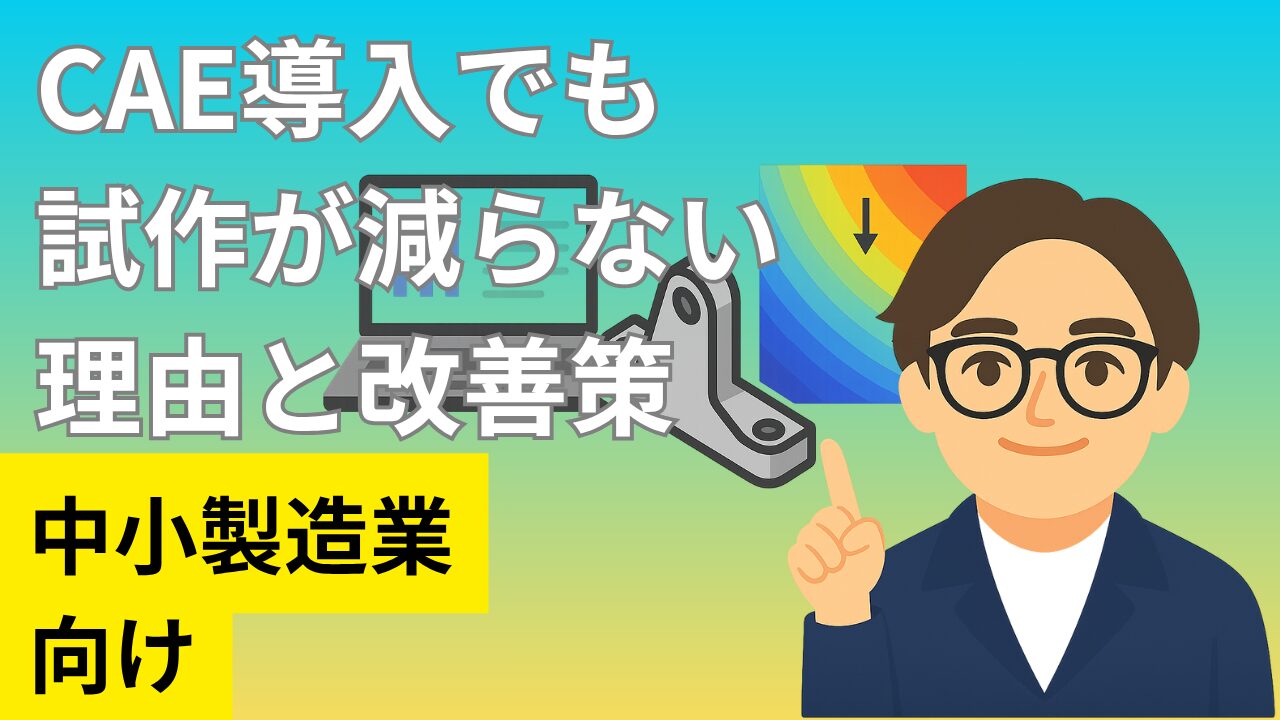


コメント